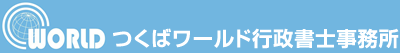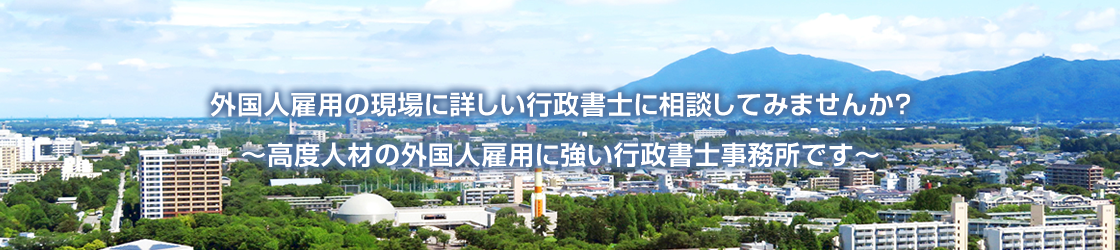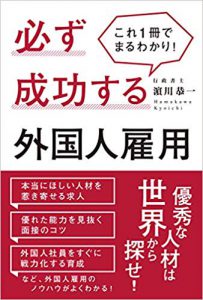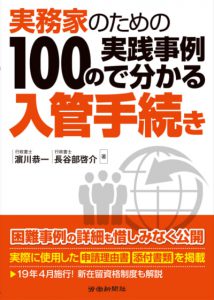就労ビザは、申請すれば必ず許可になるものではありません。その許可率は全国平均で7割程度だと言われています。ただ、不許可になったとしても、リカバリができるケースも多いです。本稿では、その方法について、分かりやすく解説します。
よくある5つの不許可理由
就労ビザ(正確には、就労可能な在留資格)の申請が不許可になってしまう原因は、大きく5つあります。その理由ごとに対策を説明していきたいと思います。なお、就労ビザは約20種類あるのですが、本稿では、不許可率が比較的高い「技人国」の在留資格を中心に説明していきます。
仕事内容が(技人国の)在留資格に該当しない
1つ目の不許可理由は、「仕事内容が技人国の在留資格に該当しない」というものです。技人国ビザは、一定レベルの専門知識を要する仕事に従事する場合に許可されます。誰でもできる仕事や反復継続性の高い仕事の場合は許可されません。この理由で不許可になった場合、申請された仕事内容が、所謂「単純労働」だと判断されています。例えば、製造業の場合、「検査」、「組み立て」といった簡単な説明だけでは、審査官が単純労働と判断してしまうリスクがあります。
この理由で不許可になった場合、仕事内容を詳細に説明し、専門知識を必要とする業務であることを立証するする必要があります。上記の例であれば、「専用の測定器を使用して検査分析を行う。この検査を行うためには機械工学に関する〇〇の知識が必要となる」といった説明をすることでリカバリできる可能性があります。
このように、単に説明不足や説明の文章が間違っていた場合は、比較的簡単にリカバリできますが、そもそも本当に単純労働だった場合(上記の例でいえば単純な目視検査)、そのままでは許可されませんので、仕事内容を変更する必要が出てきます。
申請内容に信憑性がない
2つ目の理由は、「申請内容に信憑性がない」というものです。よくある具体例としては、過去の在留資格申請時の時に記載した経歴(学歴、職歴)との整合性が合わないというものです。数カ月のずれであれば黙認されることも多いのですが、年単位で違っていたり、前回出てきていない学校名や会社名が今回突然に出てきたりすると、申請内容に疑義ありということで不許可になります。この点は容赦ないです。
再申請する場合は、正しい経歴を確認して記載するとともに、不整合になってしまった理由を説明する必要があります。審査官が見て納得する理由であれば、再申請で許可になるでしょう。
専門学校で専攻した内容と職務内容に関連性がない
3つ目の不許可理由は、最終学歴が専門学校である場合によくあります。「専門学校で専攻した内容と職務内容に関連性があるとは認められない」というものです。例えば、ウェブデザイン専門学校卒業者が、メーカーで生産管理職に従事するような場合ですね。この場合は、職種を変える必要があります。
なお、専門学校卒業後、3年(36カ月)以上、関連業務に従事している場合は、関連性要件は緩和されます。つまり、関連性については、緩やかな関連性でも認められます。稀に、審査官がうっかりしていて、このルールが適用されないことがありますので、申請時に別紙説明書などを作成し、しっかりとアピールしておきましょう。
学歴要件もしくは実務経験要件の不足
4つ目は、学歴要件もしくは実務経験要件の不足です。これは、海外の大学を卒業している場合に起こります。技人国ビザを取得するためには、原則、学士もしくは専門士の学位が必要です。海外には学位が出ない高等教育機関も多数あります。本人が学位を取得していない場合、日本の就労ビザのルールでは、学歴要件不足となります。
また、学歴要件を満たさない場合は、実務経験要件(原則10年)を満たす必要がありますが、立証する必要があります。通常、在職期間証明書だけでは認めてもらえませんので、その期間在職していたという客観的な補足証拠も準備する必要があります。
これまでの在留状況不良
5つ目は、これまでの在留状況不良です。よくある例としては、留学生時代(留学ビザで在留していた期間)に規定時間を大幅に超えてアルバイトをしていた場合です。法律的には、規定時間を1時間でも超えていると違法となるのですが、実務上は多少超えている程度であれば黙認されます。少なくとも就労ビザが不許可にはなりません。
しかし、大幅に超えている場合、就労ビザ申請も不許可になります。この場合、やむを得ない事情であれば考慮されることもあるのですが、通常は一旦帰国して、改めて就労ビザを申請することになります。不許可理由が、この点だけであれば、一旦帰国してから申請すれば、許可になる可能性が高いです。また、税金に未納がある場合も在留状況不良とされますので注意してください。
不許可理由を確認するチャンスは1回だけ
就労ビザ申請が不許可になってしまった場合、書面で通知が届きます。その書面には、不許可理由が簡潔に記載されているのですが、詳しい理由を聞きたい場合、出入国在留管理局で教えてもらえます。ただし、そのチャンスは1回だけです。後から、追加で質問したくでも一切受け付けてくれません。ですので、不許可理由を確認する際には、質問事項を整理しておきましょう。例えば、下記のような質問をすると対策が立てやすくなります。
・今回、主たる不許可理由は何か?
・主たる理由以外でマイナス要因となっている要素は何か?
・不許可理由を払拭すれば、すぐに再申請可能か?
・なぜ、追加書類が求められなかったのか?
・再申請した場合、審査期間は今回よりも長くなるか?
また、出入国在留管理局で不許可理由を確認する場合、冷静な態度で臨みましょう。感情的になったり、泣き落としを狙ったりすると、逆効果です。審査官は鬼ではないですが、かなり冷静で冷酷です。法律や内部基準に沿って粛々と審査しています。その結果が不許可です。この事実をしっかりと受け止めましょう。
ほとんどの審査官にとって、不許可理由説明というのは、嫌な仕事です。審査官が時間を取って対応してくれたことに感謝し、敬意をもって接するようにしましょう。そうすることで審査官の心証がよくなり、再申請に向けてのヒントを教えてもらえるかもしれません。
この記事を作成した人 つくばワールド行政書士事務所 行政書士 濵川恭一