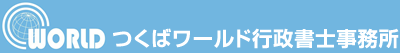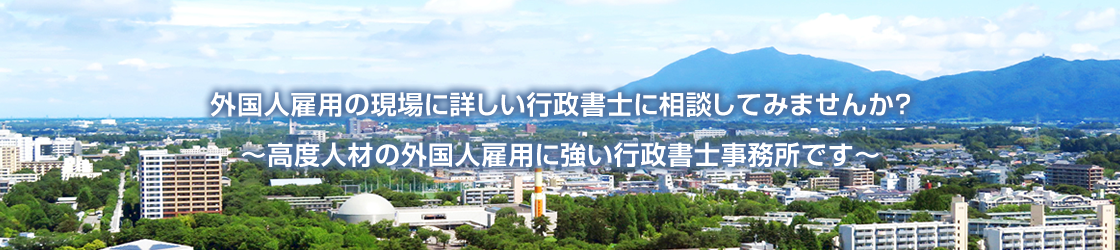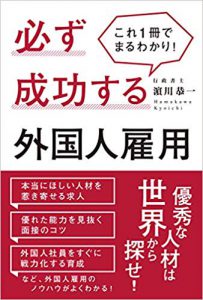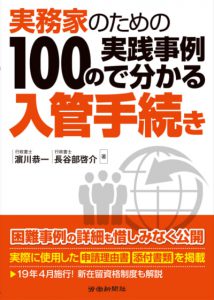国内の外国人労働者数が急増する中、まだまだ外国人雇用に消極的な企業もあります。そこで本稿では、外国人雇用のデメリットやリスクについて、改めて整理して紹介します。

在留資格や届出などの手続が煩雑
外国人を雇用した場合、原則、就労可能な在留資格(いわゆる就労ビザ)を取得する必要があります。就労ビザは、約20種類ありますが、採用する業種や職務内容によって該当するビザの種類が異なります。
就労ビザを取得するのは簡単ではありません。まず、申請に必要な書類は、10枚以上、場合によっては100枚を超えることもあります。それらの書類を収集、作成し、出入国在留管理局に提出します。翻訳が必要な書類もあります。書類に不備があれば受理されません。
ですので、就労ビザ申請に慣れていない企業の場合、ビザ申請を専門とする行政書士等に依頼することが多いですが、丸投げすることは難しいです。実際は、ほぼ丸投げということは可能なのですが、職務内容に関する最低限の打合せや会社側の書類を用意するという作業は発生します。
そのようにしてやっと申請が受理されたとしても、必ず許可になるわけではありません。今度は、審査官による厳しい審査があります。就労ビザの全国平均許可率は、80%前後です。つまり、20%程度は不許可になります。ですので、事前に就労ビザ該当性があるかどうかのリーガルチェックは非常に重要です。就労ビザが取れなければ、それまでの苦労が水の泡になってしまうからです。
就労ビザの標準的な審査期間は2~3ヶ月とされていますが、案件によっては、それ以上待たされることもあります。就労ビザがないまま雇用することは違法になりますので、採用計画が立てれらず苦労することもあるでしょう。人材会社の場合、審査が長引けば採用取消(派遣や紹介のキャンセル)という事態になることもあるようです。
また、特定技能ビザで採用した場合、法律で定められた10の支援を行い、定期的にその詳細を出入国在留管理局に報告する必要もあります。
外国人雇用に伴う費用
外国人雇用に伴う費用は、次のようなものがあります。まず、技能実習生を雇用する場合、通常は監理団体を通しますので、監理団体に支払う初期費用と毎月の管理費がかかります。これらの費用は、業種や国によって異なりますが、初期費用は50万円前後、管理費は毎月3~5万円が相場です。
特定技能外国人を雇用する場合、法律で定められた10の支援を行う必要があるのですが、この支援を外注する場合、毎月3~5万円程度の、支援委託費用がかかります。
海外から呼び寄せて採用する場合は、企業側で渡航費を負担することが多いです。社宅がない場合、会社名義でアパートを借りることも多いのですが、その初期費用(敷金礼金等)も考慮に入れておいたほうがよいでしょう。
また、就労ビザを行政書士等に依頼する場合、その費用がかかります。行政書士費用の相場は、1名の申請あたり、10~15万円程度です。
この他、求人にかかる費用があります。求人広告費、人材紹介費用などですね。求人費用については、日本人採用の場合もかかりますので、外国人特有というわけではないですが、外国人採用の場合は、採用前後に通訳が必要なケースもありますので、外国人雇用に慣れていない場合、人材会社を利用したほうがよいかもしれません。
外国人の育成の大変さ
外国人の育成は大変です。ある人事担当者は、「外国人の育成には、日本人の1.5倍の稼働がかかります。まず教えて、教えた内容を理解しているか確認して、途中経過を確認して指示を出し、その指示を理解しているかどうかを確認する必要があるから」とおっしゃていました。
私はこの言葉が非常に刺さりました。本当にそのとおりだと思います。現場感覚として、一見、日本語を流暢に話せるように見えても、100%理解していると期待すると、失敗につながります。
また、文化や宗教の違いによる価値観のギャップ、社内制度や就業規則とのミスマッチ、地域住民や既存社員との摩擦や誤解などが発生する可能性もあります。
デメリットを理解した上での採用を
当事務所でも外国人を雇用したことが何回かあります。初めて雇用した際は、就労ビザを専門とするのだから、自らも外国人を雇用しておくべきだと考え、よく考えずに採用しました。
自己流で雇用管理を行ったため、彼らの実力を十分に発揮させることができず、配慮も足りず、早期退職されてしまうことが重なりました。ただ、外国人雇用のありがたさも十分に享受しました。新しい気づきやビジネスにもつながりました。
外国人雇用のデメリットを理解した上で採用すると、メリットも十分にあります。逆に、単に人手不足だからという理由だけで安易に外国人を採用すると、皆が不幸になります。このことを知っておいていただければと思います。