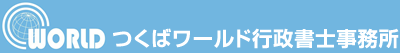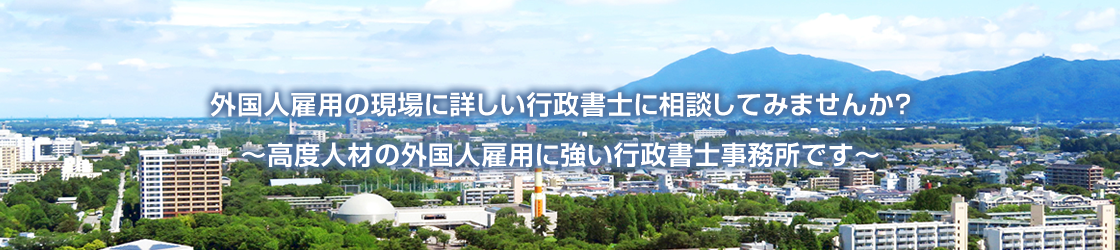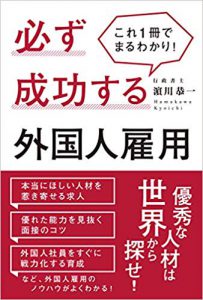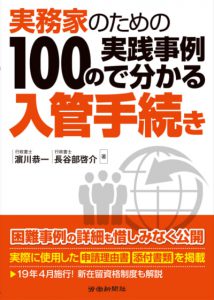この記事では、日本の専門学校を卒業した外国人留学生を採用するときの、就労ビザ(技人国ビザ)のポイントについて解説しています。
原則:専門学校で学んだ内容と職務内容の密接な関連性が必要

専門学校を卒業した留学生が、技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ)を申請した場合、専門学校で学んだ内容と仕事内容が密接に関連しているかどうかを厳しく審査されます。
一概に当てはめることは難しいのですが、概ね以下のようになります。
| 学科・コース名 | 仕事内容例 |
| ビジネス系 | 営業、マーケティング、業務管理など |
| 観光・ホテル系 | 旅行実務、ホテルのフロント業務など |
| 翻訳・通訳・語学系 | 文書翻訳、通訳、現地企業との連絡調整 |
| 簿記・会計系 | 経理、財務、経営企画など |
| 写真・グラフィックデザイン系 | 広告企画制作、画像処理、動画編集など |
| インテリアデザイン系 | 店舗、事務所のインテリアデザインなど |
| スポーツビジネス系 | 法人営業、マーケティング、企画など |
| ウェブデザイン系 | ウェブサイト、サービスの企画、制作 |
| 情報・IT系 | システムやソフト開発、プログラミング |
| 機械系 | エンジニア、開発、研究 |
| 自動車整備 | 自動車整備、自動車販売など |
| 建築・建設・設計系 | CADを用いた設計、施工管理 |
| 電子工学系 | 電子回路設計、開発 |
例外①:専門学校卒業後、3年以上関連職種に従事している場合
外国人が日本の専門学校を卒業後、3年以上、履修内容と関連性の高い業務に従事している場合は、関連性に関して例外が適用されます。
つまり、
原則:専門学校で学んだ内容と職務内容には、密接な関連性が必要
例外:専門学校で学んだ内容と職務内容には、緩やかな関連性が必要(柔軟に判断される)
例えば、専門学校でウェブデザインを専攻した留学生の場合、新卒で就職できるのは(技人国ビザが取れるのは)、原則、ウェブデザインに関連する仕事のみでした。つまり、ウェブデザイナーや、ウェブ会社での営業などですね。
しかし、専門学校卒業後、3年以上、ウェブデザイナーの仕事をしていれば、他の仕事に転職できる可能性があります。実際のビザ審査では、職務内容について細かくチェックされるのですが、この例外があるということをぜひ知っておいていただければと思います。
例外②:海外(母国など)で大学を卒業している場合
当該外国人の日本での最終学歴が専門学校であっても、母国では大学を卒業している場合があります。
この場合は、最終学歴は大学卒業となります。
ですので、専門学校で学んだ履修内容と職務内容の関連性は考えなくても構いません。大学の履修内容との緩やかな関連性があれば問題ありません。もちろん、履修内容と職務内容に密接な関連性がある場合は、技人国ビザ申請でより有利になります。
留学生の中には、日本の専門学校に通いながら、母校の大学を通信で卒業している場合もあります。この場合も最終学歴が大卒となります。
専門学校を卒業しても技人国ビザが取れないケースとは

技人国ビザに該当しない内容を学んでいる場合
例えば、「美容」「保育」「声優」などの職種は、専門学校が多くあるものの、技人国ビザの取得はできません。
なぜなら、現時点では、これらの仕事に該当するビザが存在しないからです。(特区での美容師ビザなど、一部の例外は除く)
ただし、美容や保育の専門知識を活かして、美容業界や教育業界で、営業や管理的な業務に従事するということであれば、技人国ビザを取得できる可能性はあります。例えば、化粧品メーカーでの企画、マーケティング職などです。
半分以上の単位が「日本語」「日本語能力試験対策」などの場合
半分以上の単位が日本語科目の専門学校も結構あるようです。例えば、学科名がビジネス学科となっていても、履修科目の半分以上が日本語を勉強するための科目となっている場合もあります。
こうした場合、就労ビザの審査はかなり厳しくなります。通常であれば全く問題にならない要素でも、かなり厳しく突っ込んで審査されます。
実際、出入国在留管理局の審査官から次のように指摘されたことがあります。「日本語、ビジネスマナーなどの科目は、専門科目とは認めていません。ただし通訳者養成のための日本語教育は除きます」
在学中に週28時間を大幅に超えてアルバイトをしていた場合
専門学校在学中に、週28時間(長期休暇期間は1日8時間)を超えてアルバイトをしていた場合、「資格外活動違反」という法律違反となります。
最近、技人国ビザの申請時には、前年度の住民税課税証明書(所得が記載される)が求められるようになってきました。この書類を見れば、前年にどれくらいアルバイトをしていたのか分かります。
明らかに資格外活動違反をしていた場合、技人国ビザが許可されないケースも増えています。
専門学校生の技人国ビザ よくある質問

専門学校で学んだ内容と仕事内容の関連性はどのように証明すればよいですか?
科目名が同じであっても、学ぶ内容が異なることがあります。例えば、マーケティングの科目です。A専門学校では、基本的な理論のみを学び、B専門学校では、学生が商品開発してテストマーケティングまで行う場合もあります。同じマーケティングであっても、学んだ内容は大きく違います。
高度な内容を学んでいる場合、ビザ申請の際には、成績証明書だけでなく、シラバスや教科書のコピー、レポートなども提出したほうがよいでしょう。
海外の専門学校卒業者は、技人国ビザを取れますか?
原則、海外の専門学校を卒業していても、技人国ビザの学歴要件を満たしません。ですから、実務経験要件を満たすかどうか調べたほうがよいです。
従事しようとする業務内容について10年以上の実務経験があればビザを取れる可能性はあります。
専門学校の成績はどれくらい重要ですか?
技人国ビザを申請する際には、専門学校の成績証明書を提出します。
出入国在留管理局の審査官は、履修科目と成績の両方を見ます。
つまり、学科名のみで専門性を判断するのは難しいため、どんな専門科目を履修したのかを正確に審査するために、成績証明書を見るのです。成績証明書に、仕事内容と関連する科目が多く並んでいれば、有利になります。
成績については、真ん中より上の成績を取っていれば問題ありません。全ての科目が最低評価(全科目C評価など)の場合、審査官の心証は悪くなります。仕事内容との関連性が微妙な場合、マイナスに働くことが多いです。
一方、全ての科目が最高評価(全科目S評価など)の場合、審査官の心証は良いです。仕事内容との関連性が微妙な場合であっても、総合判断でビザが許可になるケースがあります。
学校の出席率は、ビザ審査に関係ありますか?
専門学校の場合、出席率証明書というものもあります。授業への出席率が何パーセントなのかを示すものであり、出席率が悪ければ、心証は悪くなります。
あまりに出席率が悪い場合には、学校側から警告が与えられ、それでも改善が見られない場合には退学処分となることもあります。
退学処分となったことは、学校から入国管理局側にも通知されます。この場合、「在留不良」事由に該当するので、就労ビザに切り替えることはできなくなります。一度、帰国してから、一年程度の期間を経て、改めて呼び戻す必要があります。
この記事を作成した人 つくばワールド行政書士事務所 行政書士 濵川恭一